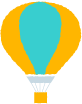一緒に食べよう!
管理栄養士 村田 貴子
7月になり北海道も夏本番を思わせる気温が続き、園では子どもたちが楽しそうに、水遊びをする姿が見られる季節になりました。4月当初は慣れない環境やクラスに戸惑いながら、緊張して給食を食べていた子ども達も、今では楽しそうに食べている様子が見られます。
毎日給食時間に各お部屋に行くと、楽しかった事を話してくれる子や、苦手な野菜に肩を落とし、無表情で固まっている子など、いろいろな表情を見ることができます。そんな中、友達や先生が「これおいしい!」「この味好き」などの言葉を聞いて、苦手なものを食べることができた、そんな感動の場面に遭遇します。苦手なものを食べることは、大人でも勇気のいることです。給食時間は「空腹を満たす」「栄養を摂取する」以外にも、先生や友達と「食卓を囲む」ことでコミュニケーションをとりながら、いろんな刺激を受ける大切な時間であることを実感します。
現代の子どもの食習慣の問題点に「孤食」ひとりで食事をする。「欠食」1日3食をたべない。「固食」いつも同じものを食べている。「個食」子どもが、大人と違うものを食べている。「粉食」柔らかい粉物の食事だけ、食べさせる、孤・欠・個・固・粉で「コケコッコ症候群」といわれています。その中でもひとりで食事をする「孤食」の多い子どもは、心と体の不調を感じやすいなど、心身の健康に悪影響を及ぼすといわれています。
「食卓を囲む」ことは日本の食文化です。一緒に同じものを食べることで安心感が得られ、何気ない会話で様々なことを知り、食事を作っている人に感謝の気持ちが芽生えます。今後子ども達に継承していくためにも、食事を共有することで得られる幸福感を大切に、給食時間が、日常の中にある大切な時間となるよう「同じ釜の飯を食う」仲間として、共に過ごしていきたいと思います。